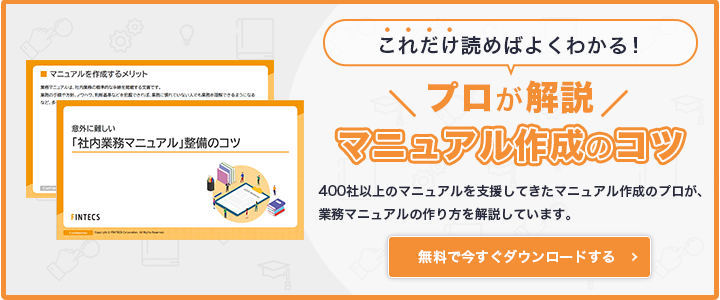マニュアルアカデミー

- ホーム
- マニュアルアカデミー
- 社内教育とは?代表的な方法と効率的に行うためのポイント
社内教育とは?代表的な方法と効率的に行うためのポイント

企業全体の成長や従業員のスキルアップを目指す場合、社内教育は有効な手段です。
しかし、「実施したものの効果を感じられなかった」「どのように進めればよいのかわからない」と悩む方もいるでしょう。
そこで、本記事では社内教育に悩みを抱えている方のため、教育を行うにあたり押さえておきたい目的や実施のタイミング、具体的な取り組み方について解説します。社内教育を効果的に進めるためのポイントを解説するので、ぜひ参考にしてください。
社内教育とは
社内教育とは、企業が従業員に対し、業務に必要な知識やスキルを提供し、セミナーや研修を実施する取り組みを指します。
日本では労働力人口の減少が続いており、今後も悪化すると予測されています。限りある労働力人口で効率よく業務に取り組んでいくためには、従業員一人ひとりのスキルアップを図らなければなりません。
個人の努力だけに頼らず、企業もスキルアップを支援する取り組みを行うことが重要です。社内教育によって従業員のモチベーションが向上すれば、人材流出を防ぐ効果も期待できます。
社内教育の目的
社内教育は何のために行うのでしょうか。主な目的は以下の4つです。
スキルアップ
社内教育の中でも代表的な目的として挙げられるのが、従業員個人のスキルアップです。一人ひとりの従業員がスキルアップすることで、企業全体としての生産性向上につながります。
スキルアップのためには、それぞれの立場や任せられている業務に合わせて、必要なスキル・知識を学べる教育を提供することがポイントです。
また、役職が上がりマネジメント業務を担当することになった場合は、これまでとは異なる知識が求められるようになります。成長段階に応じて必要となるスキルや知識を学べる機会を提供していきましょう。
これにより、「業務が難しい」「わからないことがある」といった従業員の不安を軽減できます。従業員が安心して働ける職場をつくるためにも、スキルアップの機会を提供することが重要です。
生産性の向上
生産性を高めるためには、社内教育が重要です。必要なスキルや知識を学ぶことにより、効率よく業務を進められるようになります。
特に人手不足状態にある企業では、限られた時間やリソースを有効活用するための対策が求められます。そのために社内教育が役立ちます。
業務効率の低下が生産性の低下につながっている場合は、スキルアップを目的とした社内教育を実施しましょう。従業員一人ひとりがスキルアップすることで生産性が向上し、企業の成長にもつながります。
従業員のモチベーションの向上
社内教育は、従業員のモチベーションを向上させるのにも役立ちます。研修を受けたりセミナーに参加したりすることによってできることが増えれば、それだけ向上心を持って業務に挑めるようになるでしょう。
これも企業全体の生産性向上につながります。
また、社内教育に力を入れると従業員が「自分たちは必要とされている」と感じるようになり、企業への帰属意識も高まります。やりがいや働きがいのある職場と実感できるようになれば、離職を検討する人も減るでしょう。
多くの企業では人手不足を課題として感じているため、離職防止につながる取り組みを実施することは非常に重要です。
リスクマネジメント
リスクマネジメントとして社内教育を役立てている企業も多くあります。コンプライアンス関連の意識を高めていくためには、個人情報の保護や情報セキュリティといった分野に関して正しい知識を持たなければなりません。
実際に、従業員がコンプライアンス違反を犯してしまったために企業イメージが大幅に落ち、業績が悪化してしまうケースもあります。これらのリスクを防ぐためにも、社内教育は重要な役割を果たします。
社内教育が必要なタイミング
社内教育に取り組む場合は、実施するタイミングを検討しておきましょう。代表的なタイミングとしては、入社時、配属時、昇格時が挙げられます。
また、定期的な実施も検討する必要があります。それぞれ解説します。
入社時
入社直後の従業員は業務に不慣れなため、不安を軽減し、業務に円滑に取り組めるよう社内教育が必要です。入社後の成長を早めることにもつながります。新入社員研修を実施していきましょう。
新入社員の中には、社会人としての意識が十分に備わっていない人もいます。社内教育はそういった人材に気持ちを切り替えてもらう役割も果たします。
入社時期に行われる社内教育として代表的なのは、ビジネスマナー研修やマインドセット研修などです。
また、業務への理解促進につながる研修も行うとよいでしょう。自身の役割や業務への理解が深まることで、モチベーションの向上につながります。
配属時
新入社員研修を終えて各部署に配属された際は、その配属先で必要となるスキルや知識を学ばなければなりません。ただ研修で見たり聞いたりするだけではわからない部分が多くあるため、職場で実務を通じて理解を深めていきます。
また、配属後、一定期間働いた後に、若手社員向けの研修を実施するのも効果的です。配属時に行われる社内教育は基礎的なものが中心となりますが、実際に働き始めてからは業務効率化などに関する知識も深めていかなければなりません。
業務効率を高めるには、指示を待つのではなく、自ら考えて行動する力が求められます。配属後、基本的なスキル・知識を身につけた段階で、一人でも業務を進めていけるようなトレーニングが必要です。
昇格時
昇格することで必要となる知識として挙げられるのが、マネジメントに関することです。部下を持つ立場になった際には、マネジメントに関する知識が必要です。
どのような形で従業員を育成するか考えなければならないので、そのために必要な知識を得るために社内教育を行いましょう。
研修を実施するのも効果的です。代表的なものとして管理職研修のほか、役職の階層別に行う階層別研修があります。
また、部下との円滑なやりとりには、コミュニケーション能力が欠かせません。コミュニケーション力が不足していて意思疎通に問題があるようだと、業務が滞ったり、連絡ミスにつながってしまったりする恐れもあります。
昇格後に必要な能力やスキルを習得できる機会を提供しましょう。
定期的
何かのタイミングに合わせてだけでなく、定期的に社内教育を行っていくことが求められます。常に正しい意識を持っていなければならないコンプライアンスに関することや情報セキュリティに関する分野は、特に定期的な社員研修が必要です。
社内教育の7つの種類
社内教育が必要になった際には、どのような方法で実践していくか検討が必要です。
ここでは、社内教育でよく実施される代表的な7つの方法を紹介します。自社に合っていそうなものを選んでみてください。
①OJT
OJT(On the Job Training)とは、上司や先輩が実務を通じてスキルや知識を指導する教育方法です。指導する立場にある人は「OJTトレーナー」や「OJT担当者」と呼ばれます。
特に新入社員や若手社員に対して実施されることが多い教育方法です。新入社員は、新人研修で学んだとしてもそれを実際の実務に応用するのが難しいことがあります。
OJTでは、指導者が業務を実演しながら説明し、その後、実際に業務を行わせて評価する流れになります。
現場で必要となる実践的な知識・技術が身につくことや、先輩や上司との関係性を深めて円滑な業務につなげられるといったメリットがあります。
一方で、指導者によって教え方が異なる、頻繁に行わない業務は教えにくいといったデメリットがあるので注意しましょう。
②OFF-JT
OFF-JTは「OFF the Job Training」の略であり、職場以外の場所や実務以外の時間に実施される研修のことをいいます。たとえば、セミナーなどの座学のほか、グループワークなどが代表的です。
これまでは社外で実施される集合研修が主流となっていましたが、近年はオンライン研修で学べるものも多く、自発的に従業員がオンラインで学べる環境を整えている企業も増えました。
たとえば、ビジネスに必要なスキルやマインドを習得するには、OFF-JTが適しています。
業務の中で学ぶOJTと組み合わせて行われることが多くあります。OJTの場合は一度に指導できる人数に限りがありますが、OFF-JTの場合は同時に多くの従業員に指導可能です。
ただし、研修場所に向かう交通費や、場合によっては宿泊費の支給が必要になることもあります。
③e-ラーニング
e-ラーニングとは、インターネットを活用した学習方法のことをいいます。ライブ形式で行われるものもありますが、従業員が好きな時間にスライドや動画などのコンテンツを視聴して学べるものが一般的です。
実際に人を集めて研修を行う場合は、交通費や会場費、場合によっては宿泊費などが必要となり、それらを手配するための時間もかかることになります。e-ラーニングの場合はこれらのコストを削減できることに加え、学ぶ従業員側からしても時間にしばられずに学習できるのがメリットです。
一方で、インターネットを活用するため、ITリテラシーが求められます。また、学習意欲には個人差があるため、習得度にばらつきが出る点がデメリットです。
④ティーチング
ティーチングとは、上司や先輩といった立場にある従業員が、部下に対して自身が持っているスキルなどを伝える教育方法のことをいいます。先生が授業を行うような形をイメージするとわかりやすいでしょう。
OJTのように指導者が業務を行って見せてそれを受ける側が実践するのではなく、指導者からの一方通行の形で進んでいくことになります。一対一で実施する場合もあれば、複数人を対象とする形式を採用している企業もあります。
受け手に対し、直接知識やスキルを伝えられるので、短時間で効率よく学べる点がメリットです。
一方で、指導者の教え方によって理解度に差が出る点がデメリットです。
⑤コーチング
コーチングとは、部下と対話を行うことにより、受け手の自発的な行動や思考を引き出すための手法です。ティーチングは指導者から受け手に対する一方通行の指導であるのに対し、コーチングは双方向です。
基本的に複数人を対象とすることは少なく、一対一で実施されます。
対話を通じて、本人が持つ答えや正解を引き出す手法です。そのため、指導する内容に対して全く知識がない人ではなく、すでに答えや正解を持っているまたは知っている人に対し、自身の力で正解を導き出すのをサポートする目的で行われます。
一対一形式のため、指導に時間がかかる点がデメリットです。
⑥1on1ミーティング
上司と部下が一対一で行う面談が1on1ミーティングです。主に業務のフィードバックや、キャリア開発を目的としています。
たとえば、e-ラーニングで学ぶべきことが自身でよく判断できていない部下に対し、アドバイスを行う機会としても活用できるでしょう。OJTやOFF-JTなど、その他の教育方法と組み合わせて実践されることもあります。
大きな予算や工数をかけずに実施できる点がメリットです。
ただし、事前に議題を決めておかないと、ミーティングが無駄になる可能性があるため注意が必要です。
⑦日報
業務の振り返りを行う日報は、社内教育にも活用できます。業務に関する報告だけではなく、今日の業務でよかった点、悪かった点と次回うまくやるためにどうするべきか、明日の目標は何かなど、日報の項目に加えましょう。
日報で報告を受けた疑問やうまくできずにいること、困っていることなどに対しては、適切にアドバイスを行うと効果的です。必要に応じて、他の従業員とも情報を共有しましょう。
社内教育を実施するまでのステップ
社内教育を実施する際の流れを確認しておきましょう。具体的なステップは以下のとおりです。
ステップ①組織の現状を把握し、解決すべき課題を特定する
まず、組織の現状を把握します。現状を把握すると、課題が明確になります。
改善すべき点を洗い出し、必要な社内教育を検討することが重要です。
教育が不足していると感じる部分には、重点的に時間とコストをかけましょう。
課題を特定するには、従業員へのヒアリングが欠かせません。このとき、複数の部署、さまざまな立場の従業員から話を聞くようにしましょう。部署ごと、立場ごとの課題も見つけやすくなります。
ステップ②社内教育の目的を設定する
目標を明確に設定します。あらかじめ目標を設定すると、必要な社内教育が明確になります。
目標によっては、一度の社員研修で対応できる場合もあれば、長期間にわたり複数回実施が必要な場合もあります。
なお、目標を考える際は、実現不可能なものを設定しないように注意しましょう。無理な目標を設定すると、従業員のモチベーションが低下する可能性があります。
ステップ③社内教育を実施するタイミングを決定する
いつからどのような形で社内教育を実施するのか考えましょう。明らかになった課題に対し、具体的な取り組みをスケジューリングしていきます。
複数の課題がある場合は、それぞれで検討が必要です。
具体的な実施タイミングを検討しないと、特に忙しい企業の場合は後回しになることがあります。結果的に必要なタイミングで社内教育が実施されないこともあるため、注意が必要です。
ステップ④教育の実施方法を選ぶ
前述のとおり、社内教育にはOJTやOFF-JT、e-ラーニング、その他さまざまな方法があります。どの方法で教育を行うのか考えましょう。
課題によって相性のよい教育方法が異なります。
たとえば、実践が必要な内容に対してOFF-JTやe-ラーニングでの教育を選択すると、効率が悪くなることもあるでしょう。各教育方法にはそれぞれメリットとデメリットがあるので、両方を比較した上で適した方法を選択することが大切です。
ステップ⑤アフターフォローの方法を決める
社内教育に関するアフターフォローをどのような形で行っていくか決めます。
一度の研修やセミナーで学んだことをすべて吸収できる人はほぼいません。学んだことをその場限りの知識にするのではなく、定期的なフォローアップをすることでしっかり定着させていくことが重要です。
特に研修やセミナーを実施した後は、繰り返し学習や振り返りができる環境を整えましょう。
社内教育を効率的に行うポイント
社内教育を行う際は、できるだけ効率的に進められるようにしましょう。そのためには以下のようなポイントがあります。
ポイント①社内教育の目的を明確化し、効果を分析する
あらかじめ社内教育の目的を明確に定めておくと、その目標に対してどの程度の効果が得られたのか分析しやすくなります。
効果の分析を行わずただ教育を実施するだけだと、本当に効果的な教育ができたのか判断が難しくなるので注意しましょう。数字で確認する方法のほか、従業員への聞き取り調査を行う方法などがあります。
ポイント②オンラインや動画を活用する
対面教育はどうしても実施できる機会や時間が限られてしまいます。そのため、オンラインや動画を効果的に活用しましょう。
オンラインや動画を活用できる部分は、従業員が自ら学ぶことで、指導者の負担を軽減できます。また、オンラインであればリモート勤務の人も学びやすくなります。
ポイント③必要に応じて外部に依頼する
自社だけで従業員教育をすべて行うのは大変です。そこで、必要に応じて外部に依頼することも検討してみるとよいでしょう。
たとえば、代表的な方法として外部セミナーがあります。専門性が高い内容は、自社で行うよりも専門のセミナーを提供するプロに依頼した方が、効率的で質の高い学びにつながります。
また、外部に依頼すれば、自社対応と比べて担当者の負担を軽減できます。
社内にノウハウがない知識やスキルを学ぶために活用してみてはいかがでしょうか。
ポイント④時代の変化に合わせる
時代によって適している社内教育が異なります。実際に教育を受けることになる従業員の特性や働き方も変化していくものなので、その時々に合った方法をアップデートして取り組んでいきましょう。
長年同じ教育内容を繰り返している場合は、見直しが必要です。
社内教育が企業に与える影響は大きい
いかがだったでしょうか。社内教育の概要や進め方について解説しました。社内教育を行う上で押さえておきたいポイントや、実施する重要性についてもご理解いただけたかと思います。
企業は一人ひとりの従業員によって成り立っているため、必要な教育を行い、育てることが欠かせません。
指導をわかりやすくするために、マニュアルを活用してみてはいかがでしょうか。フィンテックスでは、社内教育にも役立つ業務マニュアルのご提案・作成が可能です。ぜひご相談ください。
つい読んでしまうマニュアル作成のリーディングカンパニー、株式会社フィンテックス
監修者

企画営業部 営業本部長 / 経営学修士(MBA)
<略歴>
フィンテックスにて、マニュアル作成に関する様々な顧客課題解決に従事。
金融系からエンターテインメント系まで様々な経験から幅広い業務知識を得て、「分かりやすいマニュアル」のあるべき姿を提示。500社以上のマニュアル作成に携わる。また、複数の大企業でマニュアル作成プロジェクトの外部マネージャーを兼務している。
趣味は茶道。
月刊エコノミスト・ビジネスクロニクルで取材していただきました。ぜひご覧ください。
https://business-chronicle.com/person/fintecs.php
マニュアルアカデミー
最新コンテンツ
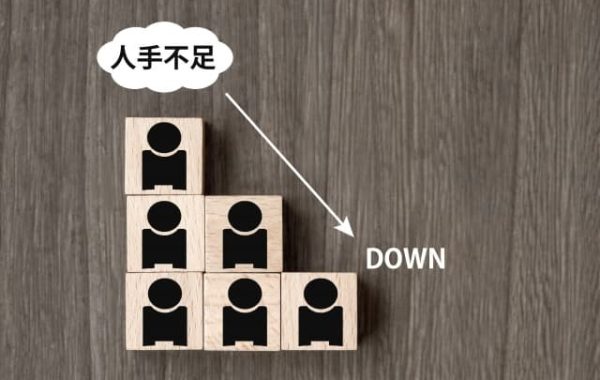
離職率が高い原因とは?考えられる主な原因と効果的な対策
2025.03.28

従業員教育しない会社は将来どうなる?今すぐ導入可能な方法をチェック
2025.03.28

人事評価マニュアルが必要な理由と作成する際に重要なポイント
2025.03.28

情報セキュリティ教育とは?自社で実践していく場合の手順と注意点
2025.03.28
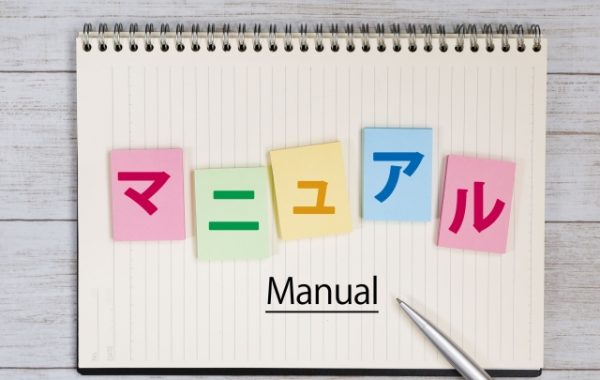
マニュアル作成の外部委託ってどう?内製との違いを徹底解説
2025.03.14

仕事の「仕組み化」とは?そのメリットと手段を解説
2025.03.10