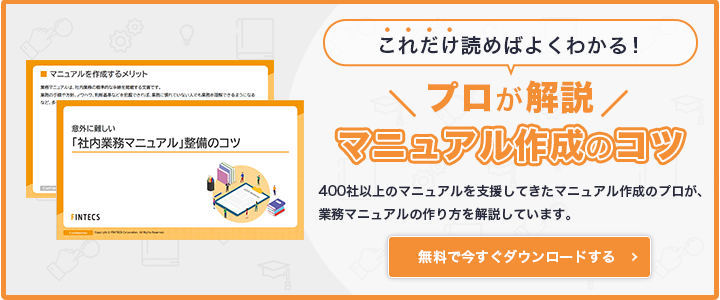マニュアルアカデミー

- ホーム
- マニュアルアカデミー
- 人事評価マニュアルが必要な理由と作成する際に重要なポイント
人事評価マニュアルが必要な理由と作成する際に重要なポイント

企業によっては、評価者が独自の判断で人事評価を行っている場合もあります。しかし、その評価方法に問題を感じている方もいるのではないでしょうか。そういった場合に取り入れていきたいのが、人事評価マニュアルです。
ただし、「自社にとって本当に必要なのかわからない」「マニュアルがあっても活用されていない」というケースもあります。そこで、本記事では人事評価マニュアルの作成を悩んでいる方のため、マニュアルが必要な理由や、作成する上で押さえておきたいポイントを解説します。
活用されやすいマニュアル作りのコツも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
人事評価マニュアルを作成すべき理由
人事評価マニュアルがない場合は、作成することをお勧めします。マニュアルを作成すべき主な理由は以下の3つです。
公平な人事評価を実現できる
できるだけ公平な人事評価をするためにも、マニュアルが必要です。人事評価の結果が納得できないと不満を抱える従業員は少なくありません。
これは「なぜ自分がこの評価なのかわからない」「なぜこの人の評価が高いのかわからない」といった状況が生まれてしまうことが大きな理由です。実際に、評価者に気に入られているなどの理由から心理的な要因が関係して不公平な人事評価が行われてしまうこともあります。
明確な評価基準を定めた人事評価マニュアルを作成すれば、このような問題を防げるでしょう。公平な人事評価を実現できます。
評価プロセスが可視化されることで、被評価者が納得感を得られる
人事評価マニュアルを作成する際は、従業員に対しても評価基準を伝えることが大切です。どのように評価されるのかを可視化することで、被評価者は納得感を得やすくなります。
正しく評価されていても、評価が低い従業員は不当だと感じることがあります。こういった場合も、どのような項目が評価の基準となるのかを明確にしておくことで納得感につなげられるでしょう。
評価者が自身の責任を自覚し、人事評価エラーの減少につながる
人事評価エラーとは、何らかの理由で公正な評価ができなくなる現象を指します。たとえば、業務スキルはないものの、コミュニケーション能力が高く従業員の中でも中心的な存在である従業員がいたとします。このような場合、「コミュニケーション能力が高い=仕事ができる」という潜在意識が生まれ、不当に高く評価されることがあります。これも人事評価エラーのひとつです。
無意識のうちに起こりやすい人事評価エラーではありますが、その理由の一つとして評価者が人事評価に関する十分な知識を持っていないことが挙げられます。マニュアルで評価項目と基準が明確になっていれば、それに即して評価することで人事評価エラーを抑えることが可能です。
また、人事評価マニュアル内で評価の結果が従業員や組織にどのような影響を与えるのかを記しておけば、評価者は自身が行う評価の重要性や責任をより深く理解できます。これにより慎重に対応するようになるのも人事評価エラーの減少につながる理由です。
活用してもらえない人事評価マニュアルとは
人事評価マニュアルは、作成するだけでは十分ではありません。作成したものの、評価者にまったく活用されていないケースもあります。
以下のような人事評価マニュアルは、活用されにくくなります。
評価基準が不明瞭なもの
人事評価マニュアルは評価基準を明確にするためのものですが、基準が不明確で評価者の参考にならない場合もあります。
このようなマニュアルは活用されず、次第に使われなくなります。
マニュアル作成者が評価基準を明確に定めたつもりでも、評価者に伝わらなければ意味がありません。
特に勤務態度や仕事への取り組み方など、数値化が難しい項目が多すぎると、評価基準が曖昧になりやすいため注意が必要です。
評価者が人事評価の重要性を理解できないようなもの
人事評価マニュアルは、評価担当者が正しく評価できるようにサポートするためのものです。マニュアルがあっても、最終的に判断するのは評価者です。
評価者自身が人事評価の重要性を理解できていなければ、適当にマニュアルを読み進めてしまうこともあるはずです。
そのため、マニュアルを活用する目的が明確でない場合、活用されない可能性が高くなります。マニュアル冒頭に人事評価やマニュアルを活用することの重要性を記しておくことが大切です。
現場の実態と合っていないもの
現場の実態とかけ離れている評価基準が記載されたマニュアルは、参考にできません。それを目にした評価担当者が「自分とは関係がない内容」と思ってしまえば、マニュアルの重要性を理解してもらえなくなるでしょう。
その結果、人事評価の際に参考にされず、使われなくなります。
内容が複雑なもの
人事評価のためにマニュアルを活用しようとしても、その内容が複雑であれば参考になりません。できるだけわかりやすいマニュアルを作成しようとして情報を詰め込んでしまったことが、複雑さにつながってしまうこともあるでしょう。
評価にはさまざまなルールがあり、評価者は自己判断ではなく、それに従う必要がありますが、細かい情報まですべて記載するとわかりにくくなるので、できるだけ簡潔にまとめることが重要です。
マニュアル作成者が1人である場合は、自身では複雑な内容になっていることに気づけないこともあります。マニュアルを完成させる前に複数人でチェックし、第三者が読んで理解できるか、簡潔に必要なことが解説されているかを判断しましょう。
長期間更新されていないもの
長期間更新されていないマニュアルは内容が古くなり、現状と合わなくなっている可能性があります。また、現状でも同様のルールが定められていたとしても、作成されたのが何年も前である場合は評価者がその内容を参考にしていいのか不安に感じてしまうこともあるでしょう。
マニュアルは、定期的に更新することが重要です。また、人事評価制度を変更した際は、それに合わせてマニュアルも改訂する必要があります。
人事評価マニュアルを作成する際のポイント
人事評価マニュアルを作成する前に、押さえておくべきポイントを確認しましょう。特に重要なのは以下の5つのポイントです。
ポイント①人事評価の目的を明確化する
はじめに行いたいのが、人事評価の目的を明確にする作業です。
そもそも、人事評価は単に個人の能力を測るためのものではありません。最終的には従業員の能力開発につなげ、企業としてさらに上を目指していくことが大きな目的です。
評価者自身がこの目的を理解し、意識することが欠かせません。まずは人事評価を行う目的を評価者に理解してもらわなければならないので、マニュアルの冒頭に記載しておきましょう。
ポイント②評価基準を透明化する
公平な人事評価を目指すためには、できる限り評価基準を明確にしておくことが重要です。これにより、評価者の印象評価によって評価が異なる事態を防げます。
基準が明確に定められていれば、非評価者としても評価結果に納得しやすくなるでしょう。
数字やデータで測れる定量評価とは異なり、働きぶりや業務姿勢を評価する定性評価は、基準の透明化が難しい傾向があります。
人事評価マニュアルでは、特に評価者によって判断がわかれやすい定性評価の基準を明確に定めましょう。
ポイント③シンプルなマニュアルを心がける
冗長で不要な情報が含まれているマニュアルは、使いにくいと判断されることがあります。そのため、できるだけシンプルに内容を記載しましょう。
よくあるのが、評価基準を透明化するために必要だと思い、あれもこれもとさまざまな情報を詰め込んでしまうケースです。このような場合は必要な情報がどこに掲載されているのかわかりにくくなり、かえって評価基準の判断を複雑化させてしまいます。
誰が読んでも理解しやすく、誤解のない内容にすることが重要です。
ポイント④人事評価制度を見直す
会社の状況や規模に応じて、人事評価の基準は変化します。
そのため、必要に応じて人事評価制度を見直す必要があります。特に長年にわたって評価制度の見直しが行われていない場合は、現在の形で問題ないか確認しておきましょう。
ポイント⑤人材育成の評価基準となるよう設定する
人事評価の最終的な目的は、個人の状況や能力を見極め、その結果を人材育成や能力開発につなげることです。そのため、単に能力を評価して終わらせず、人材育成の評価基準として活用できる内容を考えることが重要です。
たとえば、スキル向上を評価基準に設定すれば、従業員はスキル向上の必要性を認識できます。これは結果的に人材育成を促進する要素です。
評価する立場である面接官のマニュアルも必要
面接官向けの人材評価マニュアルを作成しましょう。一般的に、人事評価は面談を経た上で実施されます。
面接官が担当する面談では、従業員から評価の内容に納得がいかないと説明を求められるケースも珍しくありません。面談では、両者の評価をすり合わせる場面があります。面接官向けのマニュアルを作成すれば、面接官は何を伝えるべきか、どのように面談を進めるべきかを判断できます。
特に不慣れな面接官は、適切に内容を伝えられないことがあるため、マニュアルでサポートすることが重要です。
マニュアルを作成するだけでは不十分
人事評価マニュアルの必要性や作成する際のポイントを紹介しました。どのようにすれば、実際に活用されるマニュアルを作成できるかをご理解いただけたはずです。
ただマニュアルを作成すればいいわけではないので、公平な人事評価のために役立つマニュアルを作成していきましょう。
自社での対応が難しいと感じた方は、フィンテックスまでご相談ください。マニュアルの読み手であるユーザーを中心と考え、現場で本当に役立つマニュアルを作成・ご提供します。
自社で作ったマニュアルが活用されていない、見直しを行いたいといった場合もお気軽にご連絡ください。
つい読んでしまうマニュアル作成のリーディングカンパニー、株式会社フィンテックス
監修者

企画営業部 営業本部長 / 経営学修士(MBA)
<略歴>
フィンテックスにて、マニュアル作成に関する様々な顧客課題解決に従事。
金融系からエンターテインメント系まで様々な経験から幅広い業務知識を得て、「分かりやすいマニュアル」のあるべき姿を提示。500社以上のマニュアル作成に携わる。また、複数の大企業でマニュアル作成プロジェクトの外部マネージャーを兼務している。
趣味は茶道。
月刊エコノミスト・ビジネスクロニクルで取材していただきました。ぜひご覧ください。
https://business-chronicle.com/person/fintecs.php
マニュアルアカデミー
最新コンテンツ

社内教育とは?代表的な方法と効率的に行うためのポイント
2025.03.28
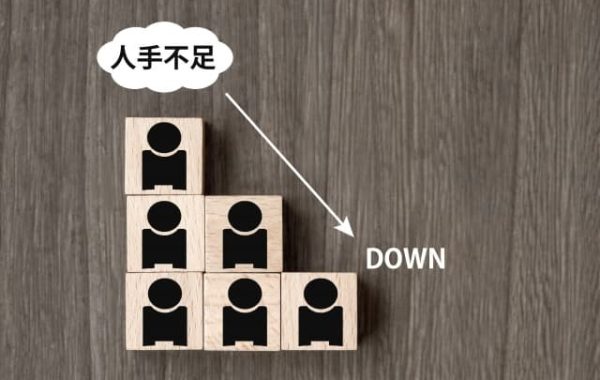
離職率が高い原因とは?考えられる主な原因と効果的な対策
2025.03.28

従業員教育しない会社は将来どうなる?今すぐ導入可能な方法をチェック
2025.03.28

情報セキュリティ教育とは?自社で実践していく場合の手順と注意点
2025.03.28
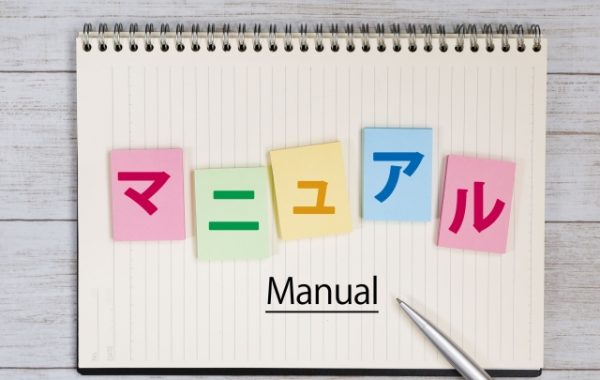
マニュアル作成の外部委託ってどう?内製との違いを徹底解説
2025.03.14

仕事の「仕組み化」とは?そのメリットと手段を解説
2025.03.10