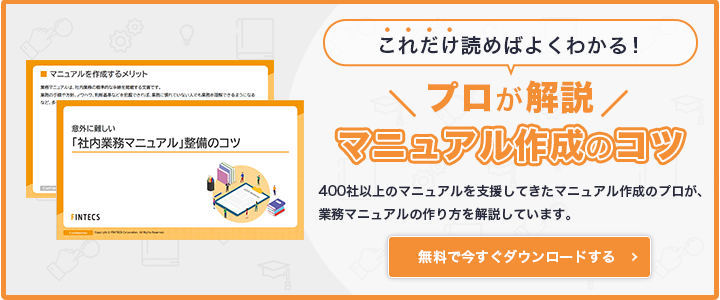マニュアルアカデミー

- ホーム
- マニュアルアカデミー
- 離職率が高い原因とは?考えられる主な原因と効果的な対策
離職率が高い原因とは?考えられる主な原因と効果的な対策
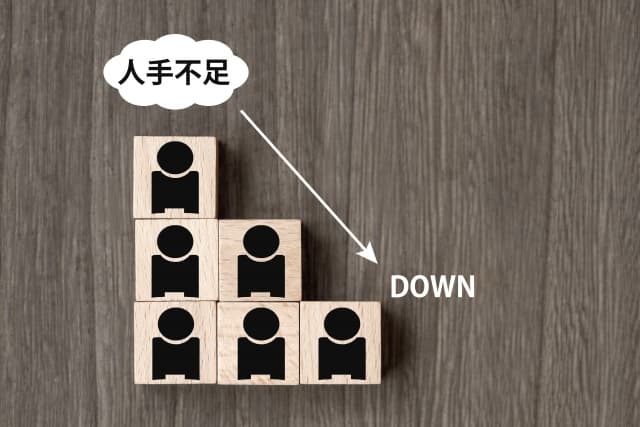
採用活動にはコストも時間もかかるので、企業として早期離職はできるだけ防ぎたいものです。しかし、「他社と比べて離職率が高い」と悩む企業も少なくありません。
そこで本記事では、離職率の高さに課題を感じている企業向けに、その原因と対策を解説します。離職率が高い状況は望ましくないため、早急に改善策を講じる必要があります。
原因を知り、具体的な対策につなげていきたいと考えている方はぜひご覧ください。離職率を抑えるためのポイントがわかります。
離職率とは?
離職率とは、一定期間内にどれだけの従業員が離職したかを示す指標です。一定期間中とは、一般的に期初から期末までの1年間を指します。
他にも、入社後1年間、または3年間といった期間で計算することもあります。また、新卒者や正社員、常時労働者など対象を限定して離職率を算出することで、入社後の定着率を分析できます。
離職率が低い企業では、多くの従業員が定着しています。一方、離職率が高い場合は辞めた従業員の数が多いことになるので、その原因をつきとめて対策をとっていかなければなりません。
離職率の計算方法
離職率の計算方法は法律で定義されているものではありません。企業によって算出の仕方が異なります。
厚生労働省の雇用動向調査では以下の計算方法を使用しているので、こちらを参考にすると良いでしょう。
離職率=離職者数÷1月1日現在の常用労働者数×100(%)
たとえば、全従業員100名の会社で、1年間に8名離職した場合の計算式は以下の通りです。
離職率=8(離職者数)÷100(1月1日現在の常用労働者数)×100=8%
また、「1月1日現在の常用労働者数」に限定する必要はなく、企業が定める期間で計算できます。期間や対象者の範囲は、企業の状況に応じて調整することが可能です。
離職率の平均
離職率を算出したら、他社と比較し、その高さを確認することが重要です。
厚生労働省が発表している令和5年雇用動向調査によると、離職率は15.4%でした。また、令和5年1年間の入職者数が約850万人だったのに対し、離職者数は約798万人です。
性別でいうと、離職率は女性の方が高い結果となりました。離職率の推移を見てみると、令和3年は13.9%だったのに対し、令和4年は15.0%まで上がり、令和5年になるとさらに高い15.4%になっています。主な離職理由は以下の通りです。
【離職理由】
- 定年・契約期間の満了
- 職場の人間関係の問題
- 長時間労働や労働条件の悪さ
- 仕事内容に興味を持てなかった
その他、個人的な理由で退職するケースもありますが、企業に対する不安や不満を理由とする離職が多い傾向にあります。
参考:(PDF)厚生労働省:令和5年雇用動向調査結果の概況[PDF]
離職率が高い企業はどうなる?
離職率が高い企業は、早急に対策を講じる必要があります。放置してしまった場合、以下のようなリスクが考えられます。
人手不足が加速する
労働力人口が不足していることもあり、人手不足に悩んでいる企業は多いようです。離職率が高いということは辞めてしまう人が多く、当然ながら企業の人手不足が加速します。
慢性的な人手不足状態になれば対応できる業務も限られてしまい、場合によっては事業規模の縮小が必要になることもあるでしょう。
また、残っている従業員が無理をして大量の業務に対応しようと考えた場合、1人当たりの業務量が増え、従業員の負担が増加します。
これは、さらなる離職を引き起こす理由にもなるポイントです。人手不足が悪化すると社員教育のための時間をとることもできず、従業員の質も低下していきます。
業務効率が悪化する
離職率が高く人手不足の状態になってしまった場合は、残された人員で業務に対応していかなければなりません。対応する従業員の数と業務量が見合っていない場合は、業務効率の悪化が考えられます。
従業員が離職すると、その担当業務を他の従業員が引き継ぐことになります。ですが、専門的な知識やスキルを必要とするポジションである場合は他の人が簡単に対応することは難しく、大幅に業務効率が悪化します。
前任者と同じスキルを持つ人材を新規ですぐ採用するのは難しいことです。後任者が育つまでの間は業務効率が非常に悪くなることが予想されます。
企業のイメージが悪化する
離職者ばかり出している企業は、どうしてもイメージが低下してしまう恐れがあります。離職率が公開されるわけではありません。
ですが、人材が不足した場合は新規に採用をしなければならないので「この会社はいつも求人を出しているな」といったところから離職者が多いことは予想できてしまいます。
また、会社に何らかの不満を持って離職するケースが多いことから、インターネットなどに悪い評価を書き込む人も多く、そこから離職率が高いと知られてしまうことも珍しくありません。
働きにくい会社と思われてしまえば、採用活動に悪影響してしまうこともあるでしょう。場合によっては取引先の企業から不審がられたり、取引を見送られたりすることも考えられます。
離職率が高くなる原因
そもそも、なぜ離職率が高くなるのでしょうか。原因を知ることで対策をとりやすくなります。ここでは、離職率が高くなる主な原因について4つ解説します。
給与への不満
給与に関する不満は離職を検討する大きな原因のひとつです。たとえば、同年代や同業他社と比較して給与が低い場合、大きな不満を感じてしまうことでしょう。より条件が良い会社に転職したいという気持ちも生まれやすくなります。
現在の給与基準に問題がないか確認が必要です。
また、自身の努力がまったく給与に反映されていないと感じた場合も不満につながります。努力が認められた社員に対しては特別手当の支給なども検討していくと良いでしょう。
更に、大変な仕事をしているにもかかわらず、それに見合った給与が支払われていない場合も離職につながります。担当している業務内容によって過酷さや負担の割合が変わってくるので、このあたりもよく検討することが重要です。
労働時間への不満
長時間労働も残業もして当たり前という時代もありましたが、今は多くの企業で労働時間を短くするために努力しています。
その中で労働時間が長いとライフワークバランスに影響を及ぼし、これが離職の原因となることも少なくありません。
人手不足であるために、どうしても長時間労働を強いることになるケースもあるでしょう。ただ、それによって離職者が増えれば状況はさらに悪化します。
こういった場合はアウトソーシングを活用することも検討してみてはいかがでしょうか。従業員1人当たりの負担を減らし、労働時間を短くすることも可能です。
人間関係の不満
人間関係の不満は、離職の直接的な原因になるほど深刻なものです。職場関係者との人間関係だけではなく、場合によっては顧客との間に問題が起こり、そこで人間関係のトラブルが発生することもあります。
高圧的な上司に対して意見を言えない、相談しにくいといった環境の場合は精神的に不安が募ってしまうはずです。パワハラやモラハラ、セクハラなどが起きているようなケースでは信頼関係を構築できず、日々の業務に支障が出ます。
性格や価値観の違う人同士が働いているので、人間関係のトラブルが起こるのはなかなか防げません。大切なのは、何かトラブルが起こった場合に相談しやすい環境が整っているか、サポートが受けられるか、だと言えるでしょう。
業務内容への不満
業務内容に不満を抱えている場合、前向きに働けません。モチベーションも低下してしまい、ただ与えられた仕事を淡々とこなすだけになる恐れがあります。
これは、従業員の性格や希望を深く考えることなく、配属先や担当業務を決めてしまった場合に発生しやすい問題です。配属先を決定する際には本人と面談を行い、どのような希望があるのか聞きましょう。
中には負担が大きく誰もやりたがらない業務もあるはずです。こういった場合も1人の従業員にすべて任せてしまうのではなく、定期的に担当者を変えるなどして対応していきましょう。
離職率が高い企業の特徴
離職率が高い企業には、共通する特徴があります。以下のような状況に陥っていないか確認しておきましょう。
長時間労働が当たり前になっている
長時間労働は従業員にとって負担が大きくなります。ですが、長時間労働が当たり前の状況では無理にでも対応しなければならず、結果として大きな不満を抱えることになるはずです。
繁忙期などに一時的な形で労働時間が長くなるのは仕方がないでしょう。まだ、毎日残業を強いられている、残業しない場合は評価が下がる、上司が帰らないために部下も帰りにくい状態になっているといったことはないでしょうか。
長時間労働をすればするだけ成果につながるとは言えません。離職率が低い会社では業務効率化に取り組み、長時間労働を防ぐための対策に力を入れています。
給料が安い
根本的に給料が安い場合、従業員がどれだけがんばっても高収入を得ることが難しく、モチベーションの低下から離職につながることがあります。
特に注意しなければならないのが「あれだけ働いたのに、これしかもらえないのか」と感じてしまう状況です。このようなケースでは、そもそも給料が業務量や業務の内容に見合っていません。
給料を上げるか、労働環境を大幅に改善するための対策が必要です。
人事評価制度が十分ではない
人事評価制度は、従業員のモチベーションとも深く関係しています。そのため、人事評価制度が十分ではないと不満を感じやすくなると言えるでしょう。
どのような評価基準なのかわからないと、自分よりも評価が高かった人に対して不公平感を抱きます。
「がんばっているのに認めてもらえない」「自分より努力していない人が高く評価されている」と感じてしまうと、前向きに業務に取り組むことはできないでしょう。人事評価制度には透明性が求められます。
教育制度が整っていない
教育制度が整っていない職場は、働きにくさを感じさせます。たとえば、新入社員向けの研修が不十分である場合、新入社員は大きな不安を感じながら業務に取り組んでいかなければなりません。
業務について十分に理解できていない状態で取り組んでいけば、大きなミスをしてしまう可能性もあるでしょう。
そのような状況が続くことを危惧して、早い段階で退職を決める人もいます。従業員にとって安心して働ける職場づくりをしていくためにも、教育制度を整えていくことが重要です。
人間関係が悪い
人間関係に問題があると、どれだけ仕事が面白かったとしてもその職場で働くのが苦痛になってしまいます。コミュニケーションをとりにくかったり、高圧的な先輩・上司がいたりする場合は業務が滞る可能性もあるでしょう。
特に上司との関係性が良くないことに悩んでいる方が多いようで「不満を伝えると評価が下がってしまいそう」と感じる場合、何か思うところがあっても我慢しなければならず、それがストレスになります。
一方、離職率の低い会社では人間関係のトラブルなどが発生した際に相談できる窓口を用意するなどして従業員をフォローしているようです。
有給休暇が取りづらい
有給休暇は従業員に認められている権利ではありますが、実際にはそれでも取りづらいケースが多く見られます。有給休暇の申請をすると文句を言われたり、嫌な顔をされたりするケースもあるようです。
また、暗黙の了解のような形で、他の人が取得していないために自身も有給休暇を取りづらいと感じることがあります。
有給休暇は何か用事があった際や、身体を休めてリフレッシュしたい際などにも役立つものです。そのため、気軽に有給休暇を申請できるような職場づくりが求められます。
ハラスメントが横行している
近年はハラスメント対策に力を入れている企業が増えてはいますが、それでもまだゼロにはなっていません。
ハラスメントが横行している状況だと、精神的なストレスを感じてしまうでしょう。出勤することが苦痛になり、場合によってはうつ病を発症してしまうこともあります。
ハラスメント対策をまったく行っていなかったり、力を入れていなかったりする場合は離職率が高くなるため、注意しなければなりません。従業員にとって安心して働ける職場であることが定着率を高める重要なポイントと言えるでしょう。
福利厚生が充実していない
福利厚生とは、企業が従業員やその家族を対象として提供する施策や取り組みのことです。福利厚生を充実させるためにはコストがかかってしまいますが、定着率の高い企業では積極的に福利厚生を充実させています。
一方、離職率が高い企業では、福利厚生にかかるコストを抑えることばかり考えてしまうようです。
福利厚生は従業員のモチベーションを高めるために欠かせないものです。やる気を出したり、働きやすくしたりするためにも福利厚生は重要と言えます。
採用のミスマッチが起こっている
離職率が高い企業では、採用のミスマッチが発生している可能性を考えましょう。採用に関するミスマッチが起こってしまうと、採用した側もされた側も「こんなはずではなかった」と感じることがあります。
そのため、採用された側は違和感や不満を抱えながら働くことになるでしょう。企業側からしても求めていた人材と違うことがわかると、扱いに困ってしまいます。
「思っていた企業(または業務)とは違った」という理由での離職が目立つ場合は、採用のミスマッチが発生していると判断できます。
業務マニュアルが整っていない
近年は若い層を中心に「業務がしっかり定義されているマニュアルは会社が用意するべき」という考え方が浸透しつつあります。特に上司からの指導に一貫性がなかったり、日によって違う内容を指導されたりすると、業務に対する違和感を持ち「マニュアルがあればこのようなことが起きないのに」と思われがちです。
「業務がしっかり定義されていない」「マニュアルが整っていない」という理由での離職が目立つ場合は、しっかりとした業務マニュアルの作成が急務になります。
離職率を抑える対策方法
離職率が高い場合は原因に応じて対策をとっていくことが求められます。ここでは、離職率を抑えるのに効果的な方法を解説するので、自社に適した方法を実践していきましょう。
人事評価制度の見直しをする
現在の人事評価制度に問題があると感じている場合は、見直しを行いましょう。業務に対し意欲的に取り組んでいる従業員でも、評価に不公平さを感じた場合、離職につながる恐れがあります。
実際には公平な評価を行っていたとしても、それが従業員に伝わらなければ同じことです。そのため、人事評価制度を見直す際には、透明性を目指していくと良いでしょう。
どのようなことが評価につながるかわかると、従業員もそれを達成しようとやる気を持って業務にあたるようになるはずです。
もちろん、評価を行う担当者が正しく評価していけるように知識を身につけることが欠かせません。評価する側の教育も実践していきましょう。
業務量の見直しをする
従業員が担当する業務量が多すぎる場合は、それが離職の原因となることもあります。当然ながら、業務量が多すぎる場合は大きな負担となるでしょう。
長時間労働を強要され、まともに休む時間が取れず疲れ果てて離職を選択する方もいます。
ただ、新規人材の採用が難しい場合は1人当たりの業務量を抑えようと思ってもなかなか難しいケースがあるはずです。業務量自体を減らすのが難しい場合は、業務の効率化に取り組んでみてはいかがでしょうか。
デジタルツールや新しいシステムなどを導入し、従業員の負担を抑えることが大切です。
職場環境を整える
職場環境を整えることにより、従業員にとって働きやすくなります。特に職場環境を悪化させる原因として挙げられるのが、人間関係のトラブルです。実際に、人間関係に問題があって職場を離れてしまう人は非常に多いと言えます。
ぱっと見ではわからない形で人間関係が悪くなっていることもあるので、何かあった際は上司などに気軽に相談できる環境を整えておきましょう。
また、普段から人間関係を良好にするための取り組みに力を入れておくのもおすすめです。
たとえば、社内交流イベントを開催したり、相談しやすい環境を作ったりするために定期的な面談を実施するなどの方法があります。人間関係以外にも職場環境を悪化させている要因がある場合は、それらを改善していくようにしましょう。
メンター制度やブラザーシスター制度を導入する
特に入社して間もない新入社員の離職が目立つ場合は、入社直後のサポートが行き届いていない可能性があります。そこで、メンター制度やブラザーシスター制度を導入してみてはいかがでしょうか。
メンター制度とは、先輩社員がメンタル面やキャリア面に関する相談役となり、サポートする制度のことです。必ずしも同じ部署の先輩である必要はありません。精神的に困ったことがあったときなどの相談先が明確であれば、何かあったときに相談しやすくなります。
ブラザーシスター制度とは、同じ部署にいる先輩がトレーナーとなり、マンツーマン形式で業務をサポートしていく制度です。業務で困ったことがあった際に誰に聞けばいいかわからないと困りますが、ブラザーシスター制度を導入しておけばそういったこともありません。
精神的な安心にもつながります。
採用のミスマッチを減らす
そもそも採用した人材が自社と合わなかったために、早期離職につながってしまうケースも少なくありません。こういったケースが目立つ場合は、採用のミスマッチを減らす取り組みが重要です。
たとえば、会社の良いところだけを聞いて採用された従業員が実際に働き始めたあとで「聞いていた話と違う」と感じると、離職を検討することになります。採用担当者によって採用基準が異なる場合もミスマッチが発生しやすくなるので、基準をまとめたマニュアルを用意するなどして、担当者に共通の認識を持ってもらいましょう。
採用後の教育やサポートが不十分だったために離職につながることもあるので、サポートに関することもマニュアルでまとめておくとわかりやすくなります。
ワークライフバランスを保つ
離職率が高いと限られた人員で業務を行わなければならず、1人当たりの負担が大きくなることもあるでしょう。
残業時間が長くなったり休日出勤が多かったりすると、ワークライフバランスを保てません。精神的なストレスを蓄積しやすくなるだけではなく、肉体的な疲労もたまります。
近年は多く稼げることよりもワークライフバランスを重視する人が増えました。環境を整えて特定の従業員にだけ業務負担が集中しないように注意し、従業員がワークライフバランスを整えられるようにしましょう。
業務の定義を固め、業務マニュアルにまとめる
しっかりとした業務マニュアルを作成することで、先輩によって指導内容が変わったり日によって指示が変わったりすることを防ぐことができます。
業務の定義をしっかりと固め、業務マニュアルにまとめることで誰でも同じように業務が行える環境を構築しましょう。
離職率が高くなる原因を特定して早期に対策をとろう
いかがだったでしょうか。離職率が高い場合に考えられる原因や、対策について解説しました。採用した従業員が安定して働ける職場環境を作っていくためのポイントなどもご理解いただけたかと思います。
育成が十分に行えていないと従業員は不安を感じやすくなり、離職してしまう恐れがあります。
対策として、業務の流れや注意点などを説明するマニュアルを用意するのも効果的です。
フィンテックスでは、各種マニュアルの作成に対応しております。業務マニュアルの作成代行だけではなく、お客様の課題を汲み取り、それを解決できるような提案を行っているので、ぜひご相談ください。
つい読んでしまうマニュアル作成のリーディングカンパニー、株式会社フィンテックス
監修者

企画営業部 営業本部長 / 経営学修士(MBA)
<略歴>
フィンテックスにて、マニュアル作成に関する様々な顧客課題解決に従事。
金融系からエンターテインメント系まで様々な経験から幅広い業務知識を得て、「分かりやすいマニュアル」のあるべき姿を提示。500社以上のマニュアル作成に携わる。また、複数の大企業でマニュアル作成プロジェクトの外部マネージャーを兼務している。
趣味は茶道。
月刊エコノミスト・ビジネスクロニクルで取材していただきました。ぜひご覧ください。
https://business-chronicle.com/person/fintecs.php
マニュアルアカデミー
最新コンテンツ

社内教育とは?代表的な方法と効率的に行うためのポイント
2025.03.28

従業員教育しない会社は将来どうなる?今すぐ導入可能な方法をチェック
2025.03.28

人事評価マニュアルが必要な理由と作成する際に重要なポイント
2025.03.28

情報セキュリティ教育とは?自社で実践していく場合の手順と注意点
2025.03.28
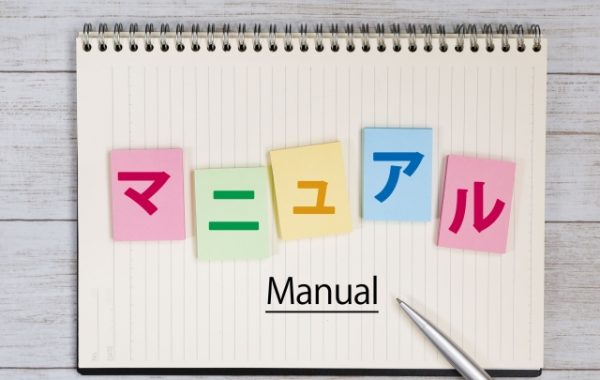
マニュアル作成の外部委託ってどう?内製との違いを徹底解説
2025.03.14

仕事の「仕組み化」とは?そのメリットと手段を解説
2025.03.10